【書評・紹介】『淡水魚保全の挑戦 水辺のにぎわいを取り戻す理念と実践』 日本魚類学会自然保護委員会
具体的な事例を元に、日本の淡水魚保全の現状と課題を探る一冊
責任編集者:渡辺勝敏、森誠一
| 読みやすさ | |
| わかりやすさ | |
| 考えさせられる度 | |
| 専門性 | やや高 |
| 電子書籍 | 無し |
内容
日本魚類学会市民公開講座での議論を基に、身近な生物多様性構成員である淡水魚の保全を積極的に進めていくための理論と実践をまとめる。様々な調査報告、研究、水辺環境の保全、保全活動の悩みなどの紹介は役立つに違いない。
淡水魚保全の挑戦: 水辺のにぎわいを取り戻す理念と実践 (叢書・イクチオロギア) | 勝敏, 渡辺, 誠一, 森, 日本魚類学会自然保護委員会 |本 | 通販 | Amazon
書評
淡水魚の保全について書かれたばりばりの専門書です。
しかしそんなに難しいことは書かれていません。
要は絶滅が危惧されるお魚たちをどうやって守っていこうかというお話です。
本書では第1部で日本の淡水魚の危機的状況と保全の方法。
第2部でタナゴ類やウシモツゴ、アユモドキなどの保全事例。
第3部でどうやって魚たちを守っていくかが述べられています。
そもそも何故絶滅危惧種を保全する必要があるのか。
色々な理由が考えられると思いますが、私は人という種がこれからも生きていくためだと考えています。
食物連鎖、食物網、食う食われるの関係。
例えば植物プランクトンを動物プランクトンが食べ、その動物プランクトンをイワシが食べ、そのイワシをマグロが食べ、そのマグロをヒトが食べるなどのことです。
このマグロの例はわかりやすいですが、生物はこの食物連鎖の中に組み込まれています。
それが絶滅してしまったらどうなるか。
家畜に害をなすオオカミを絶滅させた結果、シカの食害被害が大きくなりました。
伝染病を媒介し果実などを食害するスズメを駆除しまくった結果、バッタなどの虫による食害被害が大きくなりました。
食物網は複雑で、その生物が絶滅したらどうなるかは絶滅させてみなければわかりません。その生物が絶滅した結果、人が多大な被害を被る可能性がある。だから絶滅は避けるべきなのだと考えます。
ではどうすれば生物、本書の場合では淡水魚を守っていけるか。
ことはそう単純ではありません。
例えば在来種が減少する原因の1つにオオクチバス(ブラックバス)などの外来種の存在が挙げられます。要は在来種を食べてしまうため、在来種の数が減ってしまう。
じゃあオオクチバスを駆除をすればいい。
でもそれは、誰がやるの?どうやってやるの?費用はどうするの?
ということです。
またバス釣りの愛好家など駆除に抵抗する人物もいれば、駆除した後にまたオオクチバスを放流(違法)する人物もいる。
オオクチバスの駆除には池干し(某池の水を全て抜く番組)が有効だが、生息域が農業用の溜池の場合、近隣の農家との調整が必要。
などなど、課題はたくさんあります。
そうした課題を解消するために、専門家・地域住民・行政ら多くの人が手を組んで保全活動を行った事例などが紹介されています。
また魚の保護を考える上で近年問題となっているのが「善意の放流」です。
例えば元々生息している集団と異なる集団の放流が遺伝子汚染に繋がったり、あるいは放流によって病気や寄生虫が持ち込まれてしまったりなど、良かれと思っての行動が実は環境に良くない。
こうした「善意の放流」についても本書内で度々言及されています。
淡水魚の保全の事例について、その魚の説明、何故減少してしまったか、どう保全していったか、これからの課題などが図や写真と共にわかりやすく説明されており、この1冊で日本の淡水魚保全のあらましがわかります。
具体的な事例を元に、日本の淡水魚保全の現状と課題を探る一冊。
是非お読みください!
単行本
dorasyo329
最新記事 by dorasyo329 (全て見る)
- 【書評・紹介】『決断 生体肝移植の軌跡』 中村輝久 - 2023年9月17日
- 【書評・紹介】『休日のガンマン』 藤子・F・不二雄 - 2023年8月13日
- 【書評・紹介】『劇画・オバQ』 藤子・F・不二雄 - 2023年8月6日


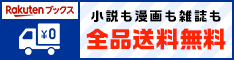


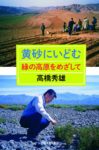
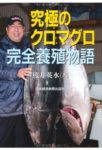

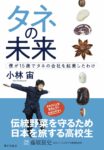

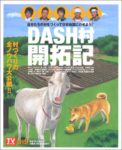


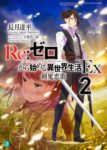
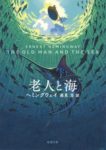
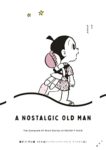

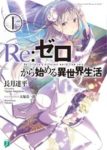

コメント
コメント一覧
まだ、コメントがありません
プライバシーポリシーが適用されます。